希望のひかり 第18回
第18回 ILC出前授業講師養成講座(第2回) ほか
市は、前回紹介した「ILC出前授業講師養成講座」の第2回を3月14日、奥州宇宙遊学館を会場に開催しました。今回は、この講座の様子などをお知らせします。
ILC出前授業講師養成講座(第2回)
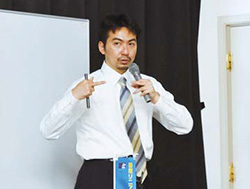
ヒッグス粒子の発見について語る石川氏本講座は、中学生を対象としたILC出前授業の実施に向けて開催したものです。今回は、東北大学大学院理学研究科の石川明正助教授が「ヒッグス粒子とILC」と題して講演。この日参加した、出前授業の講師予定者や市民など約30人は、石川氏の話に熱心に聞き入っていました。
石川氏は、素粒子物理学やILCを講師予定者によく理解してもらえるよう、素粒子物理学の歴史やヒッグス粒子などについて説明。「物は何からできているか?」という考えは古代ギリシャにまでさかのぼり、素粒子物理学は1897年にトムソンが電子を発見したことで幕を開けたことを紹介しました。電子の発見以降、加速器実験によって次々と新たな素粒子が発見され、標準理論が打ち立てられたことも解説。この理論からはノーベル賞が数多く出ており、南部陽一郎博士や小林誠博士、益川敏英博士なども受賞し、日本人研究者の貢献が大きいことも話しました。
また、2012年7月にヒッグス粒子が発見されたことで、ILCの必要性が高まったことを強調。ヒッグス粒子の性質は謎に包まれており、「本当にほかの素粒子に質量を与えているのか」「1種類だけなのか」などの謎をILCが解き明かすことで、「標準理論を超える『新理論』の姿が見えてくる」と指摘。「素粒子の謎の解明には、ヒッグス粒子が鍵。ILCでぜひ研究したい」と熱意を示しました。
石川氏は、このほか、スイスの欧州合同原子核研究機構(CERN)の大型円形加速器「LHC」と比較しながら、ILCの特徴などを説明。円形加速器ではエネルギーの損失が生じることや、LHCに比べて実験の精度が非常に高いことなどから、ぜひILCが必要だと訴えました。
また、ILCの社会的な効果として、外国人研究者などと交流できることや周辺地域の子どもたちの学力が向上し、地域活性化につながることも示唆。経済効果が約4・3兆円と試算されていることや新産業・技術の創出、人材育成につながることを述べました。
最後に石川氏は「ヒッグス粒子や暗黒物質などのノーベル賞級の研究が待っている」として講演を結びました。
いわてILC加速器科学推進会議が総会を開催

いわてILC加速器科学推進会議(亀卦川富夫代表幹事)は3月27日、新年度に向けて総会を開催しました。25年度の事業と決算を報告したほか、8月23日に大規模な講演会を開催することを盛り込んだ26新年度の事業計画と予算が承認されました。
総会後、県首席ILC推進監の大平尚氏が講演。ILCの実現に向け、東北が一体となった取り組みが重要であることを訴えました。
新年度となり、東北全体としてILCの実現へ向けた取り組みがさらに活発化することが予想されます。市は、東北ILC推進協議会や県、周辺市町村などと連携し、市民の皆さんと一緒に積極的な取り組みを実施していきます。
また、本年度も職員を派遣して出前講座を行いますので、積極的に活用してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと交流課 ILC・多文化共生推進室
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2123
ファックス:0197-22-2533
メールでのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年09月29日