11.人相を変え、江戸に潜む
46才~47才 1849(嘉永2)~1850(嘉永3)年
宇和島を逃げ出した長英は、再び江戸に戻る。長英の蘭学を活かせる地は、やはり江戸しかなかった。
長英は、人相を変え、著述を続ける。だが、その道も絶たれ、やむなく町医者沢三伯を名乗る。
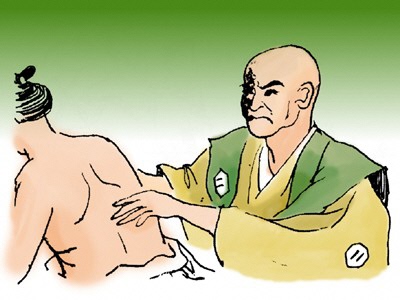
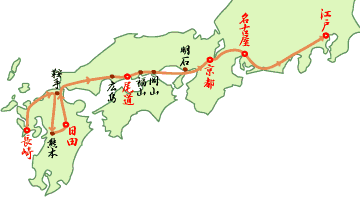
嘉永2(1849)年6月の中頃に卯之町を旅立った長英は、6月27日の夕刻、海路大阪に着き、翌日、二宮敬作、斎藤丈蔵宛の手紙を大阪宇和島藩邸に託している。7月3日の夕刻には名古屋に着き、門人の尾張藩医山崎玄庵のところに身を隠した。
その後、長英は人相を変え、江戸に入ったといわれている。高野長運著『高野長英傳』も「長英が硝石精を以て前額を烙いて人相を変へ、潜行に便じたと云ふ事は、有名な話である」としているが、そのことを伝える記録はなく、真偽のほどは定かでない。
また、江戸に戻った長英は、内田弥太郎の甥の宮野信四郎のところに一時身を隠し、その後、高柳柳助と名乗り、麻布本村町の土蔵付き差掛け小屋を借りて妻子とともに暮らしたといわれる。
ところで、長英が江戸に帰ったのは、この年の8月頃と思われ、宇和島藩江戸藩邸の官便を使って斎藤、大野兄弟にあてた8月20日付けの手紙が残っている。長英はこの手紙で江戸潜伏に危惧を持たず、逆に辺境防備について著述を始めたことを述べている。
「この節、天下の一大用は洋学に候。この節、辺防のこと甚だ急務。松前、五島等も新たに築城の命下り、また広く檄文下され良策問われ候時節柄、細かい細事を探索致すべき時に非ず。小生も不才にもかかわらず辺防の愚策申し立てべきは、この時と存じ、この節、孜々(しし つとめ励むさま)専精書き記しおり申し候。」というもので、実に大胆な行動である。
ただ、前述の手紙の送信などを見ると、宇和島から退去した後も、長英と宇和島藩の関係は密かに続いたようで、伊達宗城を通した上申を長英が考えたとしても不思議ではない。
さらに、この手紙では、「この節、例の西文二冊の傍訳訓点に取掛かりおり、来月は多分卒業と存じ候故、速やかに呈すべき候。」と、宇和島で手がけられた翻訳が江戸で完成し、宇和島藩の資金的援助が続いた可能性も指摘される。
この後、長英は下総の香取に内田弥太郎の門人花香恭法(はなかきょうほう)を訪ね、一時身を潜めている。嘉永3年(1850年)3月、恭法の留守中に置き手紙を残し、マーリンの蘭仏辞典上下2冊とホンブランドの三兵戦術書蘭訳写本を質に5両を借りてこの地を後にした。
そして、青山百人町の同心組屋敷、小島助次郎の借家を借り、沢三伯の名前で町医者を開業する。なぜ、潜伏生活から一転し、人の目に触れる機会が多い医者を開業することになったのか。
この段階で、特に捜索の手が緩む状況はない。むしろ、幕府がこの年の9月に出した洋書の翻訳と出版に対する制限は、翻訳を生活の唯一の糧としていた長英の生活を脅かすものであった。オランダ船がもたらす蘭書の購入には長崎奉行の許可が必要となった。それ以外の蘭書を扱い、または翻訳する者は、書物を没収し、所蔵者または翻訳者が処罰されるもので、長英の蘭学研究と存在意義が否定されたにも等しいものであった。
ここにいたり、長英には、危険を承知の上で、医者を開業する道しか選択の余地が残されていなかったものと考えられる。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年09月29日