2.江戸へ、17才の旅立ち
17才~22才 1820(文政3)年~1825(文政8)年
1820年、17才で兄湛斎、従兄弟遠藤養林と江戸に出て、吉田長叔の門人となり、蘭学を学び始める。
後に長叔から一字をもらい高野長英となる。

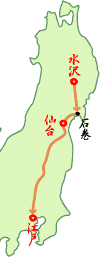
文政3(1820)年、数え年17歳のとき、長英は水沢を離れ、江戸に旅立つ。この17歳の旅立ちが長英の波瀾にとんだ人生を左右する大きな転機となる。
しかし、江戸留学は長英が強引に進めたもので、高野家、そして婚約者の千越の悲劇の始まりともいえた。留守家の医師である坂野家を継ぐための漢方医学修行の目的で、兄の湛斎が江戸に留学することになった。湛斎は坂野家の援助で留学したものと考えられる。長英は、養父の反対を押し切って、兄に同行することを承諾させたようで、養父の代理として出席した無尽講の当たりくじ15両を持って無断で旅立とうとしたとも語られている。長英と兄の湛斎は水沢から北上川を船で石巻まで下ったと思われる。石巻で従弟の遠藤養林と一緒になり、仙台を経て江戸に向かったといわれる。養林は蘭方医学を勉強し、父の遠藤養民(養父玄斎の門人)を継ぐために留学したと考えられる。したがって、長英一人が高野家の反対を押し切って江戸留学に参加した。
長英は、養父玄斎の病気見舞いに帰郷した文政6(1823)年と、弘化元(1844)年の脱獄後に前沢の母を訪ねたとされる2度をのぞき、再び郷里に帰ることはなかった。江戸留学は、結果的に、故郷水沢と決別する旅の始まりでもあった。
長英、湛斎、養林の3人は、江戸到着後、日本橋堀留町の薬種問屋、神崎屋源造のところに身を寄せた。神崎屋源造は、水沢出身で養父玄斎の知人であったといわれ、後には長英の理解者、支援者となる人物である。
希望に満ちた3人の前途には、多くの苦難が待ち構えていた。
長英と養林は、神崎屋から戸田建策のところに移った。戸田建策は一関(現在の岩手県一関市)出身の医者で、大槻玄澤の弟子であった。長英は戸田家に門人同様に扱ってもらったが、弟子入り先を見つけるまでの腰掛けのつもりで居候したことが戸田の怒りをかってしまう。困った長英は、杉田玄白の養子となっていた杉田伯元に泣きつくが、内弟子にはしてもらえず、神崎屋に寝泊まりしながら、杉田塾に通うこととなった。日中は杉田塾に通い、夜は一晩に4人ぐらいの按摩(あんま)をして200文ほどのお金を稼ぎ、茶屋で朝晩の食事をとっていた。
しかし、茶屋では朝御飯を用意できないこともあり、困った長英が兄に相談したところ、川村右仲から川村家に来るよう申し付けられ、川村家に寄宿し杉田塾に通うことになった。「実に世の中には、鬼はこれ無きものにそうろう、古人の語もこれありそうろう通りに御座そうろう」と感激を手紙に書いている。また、漢方医学の勉強を目指した兄の湛斎も簡単に弟子入り先が見つかったわけではなく、水沢からの紹介状が一本も役に立たなかったようである。
江戸に出て2年ほど過ぎた文政5(1822)年、19歳の長英は吉田長叔(よしだちょうしゅく)のもとで勉強に励んでいる。いつ杉田塾をやめ、どのような経過で吉田長叔の塾、蘭馨堂(らんけいどう)の門人になったかはっきりしない。長英は、師である長叔の一字をもらい、「卿斎」から「長英」に改名した。世に言う「高野長英」がこのとき誕生した。
吉田長叔の蘭馨堂で、長英は本格的に蘭学、蘭方医学を勉強し、薬の材料となる薬草や辰砂(水銀と硫黄の化合物)などの鉱物研究にも励み、本格的な蘭文法の勉強も始めている。また、オランダ人ヒッセルから書籍をもらうなど外国人との交流もできたようである。
この間、長英は日光、筑波山への採薬旅行やオランダ語の翻訳辞典「ハルマ和解」の要約書「譯鍵」の写本の購入などで出費がかさみ、高野家に度々送金を依頼している。養父玄斎は裕福でない家計から送金し、長英の勉学を支えたようである。
しかし、長英の蘭学勉強は平穏には進まなかった。文政5(1822)年11月頃、兄の湛斎が病気で倒れ、長英は兄の看病のかたわら診療を続け、なんとか生活していた。だが、長英の看病もむなしく、湛斎は翌年、江戸で亡くなる。長英は蘭馨堂をやめて町医者を開業する。借金返済のための開業と考えられ、収入も当初予定の半分にも満たなかった。
開業してからもまた、長英に災難がかかる。文政6(1823)年11月、長英は養父の病気見舞のため郷里水沢に帰った。3年ぶりに帰った長英に養父は会おうとせず、長英は3日の滞在で郷里を後にしたといわれる。そして、江戸に戻ってすぐの12月25日、麹町から出火した火事で、長英の赤坂の家も焼けてしまう。
また、長英が勤め口を世話し、身元引受けをした久米吉や平八郎に逃げ出されその後始末のため、中間奉公をするなどの災難が降りかかる。そんな中の8月に吉田長叔が亡くなり、長英は吉田塾を支えて奔走する。そして、長英にとって人生最大の転機となる長崎留学が翌年にやってくる。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年09月29日