4.長崎から江戸へ、開塾地を求めて
25才~27才 1828(文政11)年~1830(天保元)年
1828年、シーボルト事件が起き、多くの門人が捕まる。たまたま旅行中だった長英は難をのがれる。自分で蘭学塾を開こうと考えた長英は、西日本をまわり江戸にもどる。

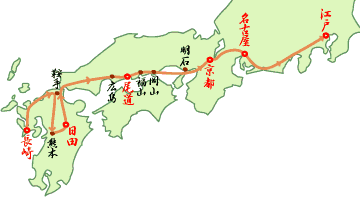
養父玄斎が亡くなり、一刻も早く郷里の水沢に帰り、高野家の跡目を継がなければならなかった長英であったが、約束した帰郷期限の養父の一周忌を過ぎても、長英は長崎に留まっていた。そして皮肉にも、長英を長崎から旅立たせたのは、シーボルト事件であった。
長英はこのとき、旅に出ていて難を逃れたとも危険を感じていち早く長崎を脱出したともいわれるが、その詳細はわからない。いずれにしろ、長英はシーボルト事件で処罰されることなく、肥後(現在の熊本県)に逃れていることがわかっている。
その後、長英は各地で診療を続けながら、天保元(1830)年5月23日、京都に到着している。『高野長英全集』の中で紹介されている長英の診療記録「客中案証」によれば、熊本を発った長英は豊後(大分県)の日田に儒学者の広瀬淡窓(ひろせたんそう)を訪ねたとされ、広瀬淡窓の塾「咸宜園」を出て世に名をなした人及び門人の名簿に高野長英の名が載っている。ただし、長英は日田には訪れず、広瀬淡窓を訪ねていないという説もある。
玄斎が亡くなって3年、当主が不在な高野家は困難を究め、長英の帰国を促すため親戚一同の手紙を持った小野良策が水沢から派遣され、尾道で長英と会った。
しかし、それから4ヶ月程後、長英は高野家との絶縁を切り出す。「長崎留学以来、多病に悩み、満足に治療術を学べず、机上の学問しかできない。水沢に帰っても医者はできないので、友人の多い江戸で療養にあたり、学問に専念したい。高野家の家督には養子をむかえ、自分は隠居したい。母は江戸に呼び寄せ、療養中ながらも孝行をつくしたい」など、これまでの期待を持たせる文面と一変した帰郷拒絶の手紙を良策に持たせた。
17歳で江戸に留学してから25歳までの9年あまりひたすら蘭学を学んできた長英の中に、日本第一の蘭学者としての自負心が芽生えていたことは当然であったろう。さらに、外国から閉ざされた鎖国時代の日本にとっての実践の学問である蘭学がいかに大事であるか、シーボルトから西洋の学問と外国事情を直接学んだ長英は痛切に感じていた。長英にとって、東北の片隅に引きこもり、留守家の医者や郷里の子弟を指導する道を選択することは、もはやありえないことであった。
最後の決断を迫られた長英は、京都で高野家との断絶を告げた後、京都から江戸に出発している。
急遽京都を旅立った理由について長英は、「学業をもって名をなすには京都はよろしからず。」と述べ、江戸の親友達から頻繁に江戸開塾を勧められたとしているが、京都での医療や開塾が思うほどの成果をあげなかったことにも原因があった。
京都を後にした長英は、途中、名古屋の伊藤圭介を訪ねる。伊藤圭介は鳴滝塾で長英と一緒に学んだシーボルトの門人である。名古屋を後にした長英が江戸の神崎屋源造方に着いたのは10月26日のことであった。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年09月29日