「森のめぐみを楽しもう~育ててみよう原木シイタケ~」を開催しました
奥州めぐみネットは、令和6年4月20日(土曜日)、水沢黒石町にある小黒石林業の作業場にて、4月イベント「森のめぐみを楽しもう~育ててみよう原木シイタケ~」を開催しました。南都田第5自治会子供会から申し込みがあり、午後の部を設けたこの日の参加者は、講師やスタッフ合わせて53名となりました。
晴れ渡った青い空の下、集合場所となった小黒石自然体験交流館「こぐりん」駐車場に、イベントを心待ちにしていた参加者の皆さんが、続々と集まってきます。

午前の部参加者の皆さん

南都田第5自治会子供会の皆さん
最初に注意事項などをお知らせし、いざ山中の会場へ。途中の作業道では車の乗り入れに苦労する場面もありましたが、無事に到着。事前に準備された切り口も新しい丸太の作業台が、参加者を迎えます。周囲には山桜の白い花もまだ残り、新緑と合わせて、森の中にいる気持ち良さを体感。

今回の講師は、当会の運営委員で小黒石林業代表でもある千田正典さんと、奥州地方森林組合の佐藤美加子さんです。

作業に入る前に、講師の佐藤さんから、岩手の森のめぐみや森林にかかわる仕事、森林づくり県民税などについてお話をお聞きしました。

森林がもたらす命の育み、防災につながる保水調節機能について、森林を守るための施策があることなど、私たちが生活する中で何気なく享受している豊かさについて、認識を深めました。
さて、いよいよお待ちかね、シイタケ植菌作業です。1本のほだ木には、3列・各7個ずつ穴をあけて、種駒を打ち込みます。講師の千田正典さんの電動ドリルの模範実技を見た後、参加者の皆さんでそれぞれほだ木に穴をあけていきます。




安全面を考慮して、子どもは大人と一緒に作業することとし、3台あるドリルにはそれぞれスタッフが付き添います。発電機の爆音が響き渡る中、皆さん手元に一点集中。丁寧に穴をあけていきます。
穴あけが終わると、丸太の台座に移動してシイタケの種駒を金槌や木槌で打ち込んでいきます。今回使用した種駒「にく丸」は、その名のとおり肉厚で春秋に収穫できることが特徴の品種で、乾燥保存にも適しています






出来上がったほだ木には名前を書いたテープが巻かれ、並べられていきました。
最後に、講師の佐藤さんからシイタケ栽培の仕方、主にほだ木管理について説明を受けました。原木シイタケが収穫できるまでには1年ほどかかり、約3年間にわたって収穫ができるそうで、栽培は光がちらちらと差し込む場所で適度に水を与えながら管理するのだそうです。
参加者からは「収穫までに一年かかることを今回初めて知った」「作業も楽しかったが収穫も楽しみ」などの感想が寄せられました。




その後は、小黒石林業で栽培している原木シイタケや会場近くにあるビオトープを見学。日差しで温まった水の中には、オタマジャクシのほかゼリー状の袋に包まれたサンショウウオの卵も見ることができて、貴重な機会となりました。

イベントを通して、以下のSDGsの目標について考えました
【質の高い教育をみんなに】

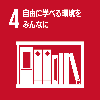
原木シイタケについて学ぶとともに、森の役割やそのめぐみについて理解を深めました。
【気候変動に具体的な対策を】


原木シイタケの性質や育て方を知ることで、気候や環境に合わせて栽培管理できるようになりました。
【陸の豊かさも守ろう】


春の森のめぐみを感じるとともに、山中にあるビオトープならではの生き物たちに出会うことができました。
【パートナーシップで目標を達成しよう】


講師の指導を受けて、大人も子どもも参加者みんなで一緒に取り組みました。
奥州めぐみネットでは、イベント実施のほか環境学習のサポートも行っています。
市内の企業、団体、地域コミュニティ、学校など、興味のある方は市生活環境課環境係(0197-34-2340(直通))までお問い合わせください。








更新日:2024年05月27日