8月イベント「水のワークショップ」を開催しました!
奥州めぐみネットは、令和7年8月9日(土曜日)、胆沢若柳にある胆沢ダム管理事務所内の胆沢ダム展示室にて、8月イベント「水のワークショップ」イベントを開催しました。
今回は、午前の部、午後の部に分けてイベントを行い、参加者は計32名(講師・スタッフを含む)となりました。
「胆沢ダムの概要」の講師は胆沢ダム管理事務職員、「水のワークショップ」の講師は水と生きるSUNTORYです。

午前の部

午後の部
イベント前半は、会場である胆沢ダムの概要を学びました。
胆沢ダムがどのような過程でつくられたのか、どのような役割を担っているのか、などを学びました。また、私たちの生活に密接にかかわっていることがわかりました。


また、雨の少ない現在の状況から貯水率が20%を下回り、イベント当日に胆沢ダムとして過去最低の貯水率になったとの話がありました。


イベント後半は、SUNTORYによる「水のワークショップ」を行いました。
はじめに、SUNTORYが何を行っている会社か、水資源の大切さについて学びました。


水資源の大切さについて学んだ後に「マーブリング」を行いました!今回は、コースターを作りました!
5色の絵の具から好きな色を選び、絵の具を綿棒に吸収させて優しくそっと水面に色を浮かべます。


絵の具を吸収した綿棒を水面につけると、絵の具の色が混ざらずに各色が水面に浮かんでいました。
好きな色を水面に浮かべたら、爪楊枝を使用し、浮かんでいる絵の具でマーブル模様を作ります。マーブル模様が細かくならないよう、爪楊枝をゆっくり水面を撫でるように動かしました。


マーブル模様ができたら、コースターに模様を転写します。
コースターをすべて沈めないこと、水面につけるときにコースターを傾けないことに注意し、転写したい模様の水面に、コースターをつけました。


コースターにマーブル模様を転写し、コースターを水面から離します。1、2、3秒数え、コースターをひっくり返すと、みなさんマーブル模様がしっかりと転写されていました!


転写した模様が安定する(乾く)まで、SUNTORYと水の実験を行いました。
私たちの街を表現した(山、川、町、海)実験装置を使用しました。
人が手入れをしているAの森(地面に日光があたり、草が生い茂っている)、人が手入れをしていないBの森(木が多くあり、地面に日光が当たらない)、どちらの土が水を貯え、ろ過に適しているのか考え、実験で検証しました。


まず実際にAの土、Bの土を触って比べました。
子ども達から、Aの土は「ふわふわしている。ガーデニングの土みたい。」、Bの土は「校庭の土みたい」と感想が上がりました。
実際に雨水に見立てた濁った水を、Aの土・Bの土に雨を流していきます。
すると、Aの土は水を吸収し、ろ過が行われますが、Bの土は水が吸収される前に土砂崩れを起こしてしまい、町に土砂が流れてしまいました。
手入れがされている微生物や空気を含んだAの土を通った水は、ろ過が行われたため、雨として流した水よりきれいな水が川から海へ流れていました。




実験装置を使用し、土の重要性を学びました。
私たちがお店でよく見るSUNTORYの「天然水」は20年以上かけて地下深くで磨かれた水が使用されているとのことです。
SUNTORYは、これから先もおいしい天然水が飲めるように、たくさんの専門家と協力して、水を貯える、水をきれいにする森をつくる「サントリー天然水の森」活動を全国各地で行っているそうです。




SUNTORYのきれいでおいしい天然水を育む活動について、学ぶことができました。


みなさんのコースターにはマーブル模様がきれいに転写されていました!
午後の最後には講師の皆さんを含め、記念撮影を行い、イベントを終了しました。
参加者から「胆沢ダムの歴史や機能を改めて知ることができた。地元の胆沢ダムのことを学べて良い機会になった。マーブリング、コースター作りが楽しかった。SUNTORYの水の実験、模型がとてもわかりやすかった。」などといった感想が寄せられました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
イベントを通して、以下のSDGsの目標について考えました
質の高い教育をみんなに / 自由に学べる環境をみんなに


地元の胆沢ダムの役割、水の繋がりについて学びました。
安全な水とトイレを世界中に / きれいな水を今も未来も


これから先もきれいな水使うことができるようにするための取り組みについて、理解を深めることができました。
パートナーシップで目標を達成しよう / みんなが「つながる」まちづくり

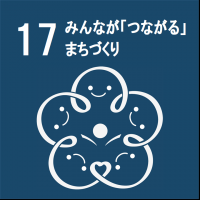
SUNTORYの皆さん、胆沢ダム管理事務所の皆さんの協力を得て、楽しく学ぶことができました。ありがとうございました。








更新日:2025年08月22日