奥州羅針盤(4年6月)
まちづくりを議論する上で、周産期医療(妊娠22週から出生後満7日未満までの医療)は大切な要素です。
私はこれまで延べ25人以上の医師にお会いし、意見を伺いました。出産できる施設を新設するためには、産婦人科医を最低でも5人、そこに小児科医、外科医、麻酔科医のチームが必要ですし、助産師、看護師も確保しなければなりません。加えて、ハードルをさらに高くしているのは、分娩時の医療事故に対する訴訟問題と医師の働き方改革です。県内における周産期医療体制の現実は、既に危機的状況にあります。
そこで、私は当面の間、県南地域における周産期医療を守ることに重点を置いて「里帰り出産」と「安心できる出産」の意味についてプロジェクトチームで議論しました。そして、少なくとも次の5つのサポートが必要だと感じています。
- 出産直前まで市内で妊婦健診ができる体制づくり
- 市外の病院と妊婦健診の結果を正確に共有できる仕組み(電子カルテと遠隔医療システム)
- 妊婦の安心・安全な移動の配慮(研修を受けたタクシーや移動型医療車両の利用)
- 出産に関わる経済的支援
- 出産後のケア(産後ケア事業、赤ちゃん訪問など)
市立病院にこれらの周産期サポート機能を新設することで、「安心できる出産」は可能になると考えます。ただし、私は市内で出産できる環境づくりを諦めてはいません。今後、この取り組みを推し進めることで、これに賛同する産婦人科医の招へいや、産婦人科医を志す医学生の長期育成計画も可能となります。
まずは、高い目標値を実現するために、最初のステップを着実に踏み出します。
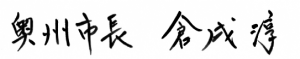
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-








更新日:2023年09月29日