奥州羅針盤(5年3月)
今回は、農学部在籍時代を思い出して、農業にチョイとうるさいオッチャンの立場で意見を述べます。
2021年の日本の食料自給率は、生産額ベースで69%、カロリーベースで38%と発表されています。ロシアのウクライナ侵攻以来、食料の安全保障の重要性が叫ばれ、自国ファースト主義が高まっている中、この数字は危機的状況です。
さて皆さん、この数字に一つ落とし穴があることに気付きましたか? そうです、国内の自給率を正確に表すには、肥料や飼料の国内調達率を考慮した食料国産自給率が重要な指標になります。ちなみに、カロリーベースで畜産物の自給率は64%ですが、飼料の輸入分を差し引くと16%です。鶏卵にいたっては、国内生産率は98%ですが、飼料を輸入に依存しているため、国産自給率は10%程度です。現に飼料価格の高騰で、卵の価格は上がっており、前途多難です。
アメリカへの依存が高い小麦、大豆、トウモロコシの場合は、別なリスクもあります。小麦は、大穀倉地帯から太平洋側に運ばれ、そこから日本に輸出されますが、大豆やトウモロコシは、パナマ運河を通して太平洋に入ります。この運河がくせ者です。地球温暖化の影響で中流の水位低下が激しく、大型船が通過できないため物流コストが上がります。加えて、トウモロコシ農家は、日本に輸出するよりも有利な条件で販売できる、米国内のバイオエタノール燃料としての交渉のカードも握っています。日本の飼料メーカーにとっては三重苦の状況です。
国際情勢が複雑な中での難しいかじ取りは他人ごとではなく、われわれの身近に迫っているのです。
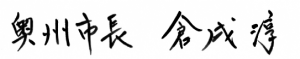
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-








更新日:2023年09月29日