奥州羅針盤(4年11月)
日本の農業就業人口は、全人口の1.3%まで縮小し、農家の平均年齢は67歳まで上昇しています。それでも逆転の農業の発想を持つと希望はあります。これまでも、農業法人の若い経営者が唱えた「新3K宣言(稼げる・カッコイイ・感動がある)」を頼もしく感じたように、よく目を凝らして農業を見てみると、「心が折れる」悲観的な状況だけでなく、未来への新しい息吹を感じ取ることができます。
日本では、21世紀に入って農業の構造変化が起こっています。本来は農家の世帯収入を増やし、社会の安定に貢献してきたはずの兼業農家の仕組みが、農業の担い手を確保することに失敗し、急速にその存在感を失っていったといわれています。その一方で、6次産業化によって農業法人が躍進しています。モノづくりの強みを生かし消費者に直接商品を届ける仕組みが、農業の収益性の低さからの脱却につながりました。
奥州市の農業の方向性を議論するためのたたき台は、「稲作は大規模&スマート農業化、野菜・果物・生花は6次産業化」と単純化した上で、農事組合として何ができるか、行政としてどのようなサポートが必要かを建設的に議論することが重要ではないでしょうか。
奥州市は県内一の耕地面積を誇り、全国的に通用する数々の農畜産物ブランドを持っています。この強みを生かした戦略を創りあげた上で、ベテラン農業者の熟練の技と、新進気鋭の農業者のマーケティング力をうまく融合できる地域が発展するのでしょう。
農業を身近に感じる国民が増えることが、国の食料安全保障体制を強化する近道なのかもしれません。
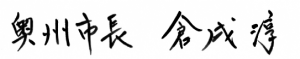
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-








更新日:2023年09月29日