牛の博物館友の会 活動
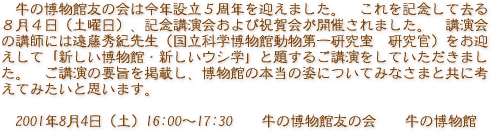

- 国立科学博物館・動物研究部
遠藤 秀紀(えんどうひでき) - 略 歴 1965年生まれ。
国立科学博物館動物研究部研究官 獣医学博士。
専門は比較解剖学。
「博物館が面白い」とされる時代です。しかし良くも悪くも、博物館は大きな岐路に立たされているような気がします。博物館とは何なのか? 私たちは博物館にどういう未来を期待することができるのか? 今日はフロアの皆様といっしょに、楽しくかつ真剣に考えたいと思っています。

世界最大の博物館も入館者数は
東京ディズニーランドに及ばない
東京ディズニーランド。唐突ですが、この遊園地は、毎年1700万人のお客さんを集めます。開園以来20年間で2億人を越える入園者数を記録しました。横浜の八景島シーパラダイスが毎年650万人、同様に長崎ハウステンボスが400万人、テーマパークのこの数字がもつ意味はいったい何なのでしょう?
一方で博物館ですが、ここ前沢の牛の博物館は、毎年2万5000人くらいの来館者を迎えています。私の所属する国立科学博物館は東京上野公園にあって、例年だいたい70万人という数が見えてきます。年間100万人に達することはとても難しい状態です。公立の社会教育機関でとりわけ入場者数が多いのは、東京都恩賜上野動物園ですが、それでも毎年350万人ほどです。
いきなり卑近な例を話しましたが、こういう数字の比較で遊んでみたのは、皆さんにひとつのことを理解していただきたいからです。それは、「博物館の社会的任務は、民間エンターテインメント企業の営業とは異なる」という明確な内容です。
昨今の行政改革ブームでは、国や自治体の将来を見据えることよりも、弱い立場の公的責任を平気で投げ出すことが行われています。国立の博物館・美術館は、独立行政法人化されました。国の試験研究機関も同様です。さらには国立大学まで法人化とともに、統廃合、縮小を重ねる様子が見えてきました。合理化されていく博物館が、国や自治体から確実に求められるものが、入館者数を増やし、社会に貢献したという、見せかけの生産性のアリバイなのです。逆にいえば、入館者数さえ増やしていれば存続させるが、お客さんの来ない館は廃止する、という国政の未来像が、ここに現われています。
では、本来の博物館の責任とはどういうことなのでしょうか?
博物館の責任は大きく分けて2つ、「研究」と「教育」があげられます。ここでは「研究」を切り口にして見てみましょう。

2トンを越える遺体は運ぶにも一苦労だ
私が得意とするのは解剖学です。生きとし生けるものは、ヒトもウシもイヌもネズミも、みな死にます。解剖学は死んだ動物の遺体を収集することから始まります。365日24時間、生命を落とした動物の元へかけつけるのが、私の仕事です。仕事場の中心のひとつは、動物園の解剖室といえます。炎天下にゾウが倒れても、お正月にサイが息を引き取っても、それを博物館へ運び、解剖してデータをとり、論文に出版するのが、プロたる学者の仕事です。そして、その遺体を、例えば骨格や毛皮などの標本につくりあげ、未来永劫保存することが、博物館の責務なのです。さらにその標本の情報を整理して公開し、世界中の人々の研究のために尽くすことが、博物館の重要な貢献となります。
これをオーソドックスに貫き通して、私はいくつかの論文を発表してきました。
例えばジャイアントパンダの掌を解剖した成果は世界的に評価されました。イノシシの頭 蓋骨、ゾウの腎臓、キリンの頸、トラの顎、アザラシの顔面など、四六時中遺体を集めてそこから何ができるかを考えてきた私は、本当にさまざまな動物の解剖学を進めて世界に発表し、同時に遺体を標本化することに成功しました。

手にしているのはジャイアントパンダの頭部
こういう営みは、社会に対してたいへん多くの知的財産をもたらしたと確信しています。一連の息の長い仕事を、私は誇りに思うことができるのです。
ところが、国の仕事の中で、「研究」をとてもきびしく管理する動きが生じていて、それは行革ブームで際限なく加速しています。いま学者は、「あなたは毎日24時間、どれほど市民や社会に貢献するために、自分の研究の時間を減らすことに“成功"していますか」という問われ方をします。普通の学者は、税金からお給料をいただき、税金から研究費を受け取ることが圧倒的に多いわけですが、そのことと引き換えに、研究の遂行を厳しく管理されるようになりました。その行き過ぎた形が博物館のような社会教育機関に現われています。
今日国中の博物館では、たとえば年間研究費が3万円という学芸員が普通にいるのです。それは行政から「あなたは研究をやめなさい」と言われているのに等しいといえるでしょう。その一方で、毎年何十億円という税金が、ヒトゲノム解読やタンパク質の構造解析のために、民間組織に投入されてきています。これらの“研究"は、国が“国策"と位置付けたもので、“特許や経済基盤で日本が遅れをとらないように"、という批判を受けにくい大義名分に守られています。
そういう潤沢な“研究"の裏で、各博物館は、まるで遊園地を模倣するかのような入館者数増大のみを求められ、「研究」は“3万円"に軽んじられています。大学も国家間競争に関わらないような部門は、縮小を余儀なくされていくことでしょう。
皆さんが普段博物館と接する機会は、博物館のもう一つの責任である「教育」の場面だろうと思います。その大事な部分に展示場があります。フロアの皆さんにひとつお勧めを致します。「研究」を軽んじる博物館がいかに無意味で味気ないものであるかを、ここでよく考えてみてほしいのです。皆さんは、牛の博物館や国立科学博物館の展示場が、エンターテインメント遊園地と異なることにすぐ気が付くことでしょう。何がもっとも違うかといえば、博物館の教育・展示は、「学問」によって、つまり真実を求めて闘ってきた学者たちの命懸けの「研究」の上に成り立っているということです。博物館の「教育」は「学問」でなければなりません。それは、お客さんを集めることを至上命題にしたバナナの叩き売りでもないし、スーパーのバーゲンでもないし、もちろん、ネズミのぬいぐるみが演じる空想世界の“商品"ではないのです。

島の斜面で暮らす在来牛だ
前沢町が誇る牛の博物館。この施設の存在意義の第一は「ウシ学の発展」でしょう。そして展示やレクチャーによる社会教育は、その成果を示す大切な場です。牛の博物館の責任は、民間の遊園地と人の入りを競うことではありません。地に足をつけて、息の長い研究と教育を続けることが、その何より大切な責任なのです。
博物館の「学問」を相手に、“商品"と同等の生産性を求めることが、政治や行政の手で普通に行われる時代になりました。教育機関の税執行の正しさが、来館者数アップのようなエンターテインメントへの迎合によってのみ評価されると考える、恐ろしく愚かな手法によって、国中の研究と教育が翻弄されています。本日は、そういう乱暴な現実を見据えながら、末永く文化を支える博物館の本当の姿を、皆さんといっしょに考えることができれば幸いに思います。
