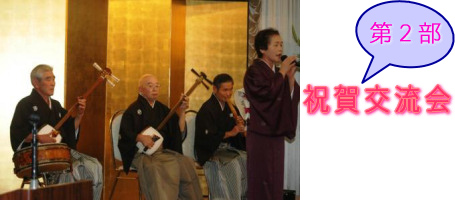牛の博物館友の会 活動
博物館フォーラム「市民に開かれた博物館」基調講演資料
前沢に牛の博物館がオープンした翌年、博物館を支援する目的で「牛の博物館友の会」を設立して、今年でちょうど10周年になります。
地域に根ざした活動を続けてきた友の会が、もっと市民に愛されるために、また、もっとみんなに開かれた博物館となるために、10周年記念事業を催します。
生涯学習の時代にあなたも参加して、地域文化創造の一翼を担ってみませんか!
2006年10月29日 10::00~12:30 牛の博物館友の会 牛の博物館

- NPO日本語教育研究所理事長
上野田鶴子(うえのたづこ) - 言語学博士
放送大学客員教授
日本語教育研究所理事長
元東京女子大学教授
牛の博物館友の会会員
- 1「ことば」とコミュニケーション
- 「ことば」は人間を特徴付けるコミュニケーション手段であり、聞いたり話したりする音声言語と、読んだり書いたりする文字言語の側面をもつ。世界中には何千という言語があり、文字のない言語はあるが、どの言語も音声を用いる。
- 2 感覚とことば
- 聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚の五感覚は耳、目、手、舌、鼻を用いる。
「ことば」によるコミュニケーションには、聴覚が音声言語に視覚が文字言語に重要な役割を担っている。文字を書くには手が役割を担っている。

- 3 ことばの獲得・発達・喪失
- 脳の左半球(左脳)と右半球(右脳)の役割:左半球は分析的(言語や数字の操作)認知に関与し、右半球は総合的(視空間認知)認知にかかわる。
ことばの獲得・発達・喪失(失語症など)には左半球にある言語中枢、言語野、前頭部、後頭部が関与し、耳・口・目・手は入出力を担う末端の器官である。 - 4 聴覚障害と視覚障害
- ことばの発達と聴覚障害・視覚障害:手話/読唇 と 点字
聴覚は最も早く発達し、最後まで残る。聴覚障害は言語獲得・発達に影響する。
視覚障害は音声言語の獲得が可能。言語発達は10歳前後に臨界期(critical period)を迎えると考えられている。第一言語(母語)の鋳型を身につける時期である。話しことばの獲得、書きことばの習得において重要な時期である。「9歳の壁」といわれる時期と重なる。 - 5 ことばの4技能
- 音声言語に用いられる「聞く」、「話す」、文字言語に用いられる「読む」、「書く」の4技能のうち、聞く・読むは「理解」に必要な技能であり、話す・書くは「表出」に必要な技能である。理解力は表出能力の前提となる。
- 6 話しことばと書きことば
- 話しことばは多くの情報を時間内に伝えることが可能であるが、音声は瞬時に消えていくため、短期記憶から長期記憶への意味処理も瞬時に行われる。
書きことばの場合には文字列を追って意味処理を行うが、文字は消えないで残るため理解の困難な場合には繰り返し読みを行うことができる。 - 話しことばの場合も書きことばの場合にも、理解のプロセスにおいては、ことばの連鎖のみを対象として理解するのではなく、常識や経験に基く「知識の枠組」(スキーマ)や物事の「筋書き」(スクリプト)を受け皿として用意し、予測や推論を用いて、意味解釈を行なう。従って、常識の有無、経験の違いによって理解のあり方が異なる。「行間を読む」、「ジョークがわかる」、「京のぶぶ漬け」
- 7 日本語の特徴
- (1)話しことばと書きことばの違いが大きい。
音声言語は音節数も少なく文法も比較的簡単だといわれるが、文字言語にはひらがな、カタカナ、漢字等を用い、表記方が極めて複雑で習得が難しい。 - (2)日本語は文脈や場面に依存度の高い言語である。
話し手と聞き手あるいは書き手と読み手の関係(相互の役割)場面(公的/私的)によってことばの使い方、選択が変わる。 -
- 人称の選択(わたし-あなた、ぼく-きみ、おれ-おまえ、きさま)
- です/ますの選択(文体)、敬語の使用
- 「誰が、誰に、何を」の部分を明示しない場合がある(省略する)。
- 文末に述部が用いられるが、文末も省略する(そうするかも。どうも。)
- 相手に合わせたやり取り(そうですね。でも・・・・・・)
- よろしくお願いします(前置き表現)
- (3)和語、漢語、外来語、カタカナ語
- 8 ことばの持つ力を発揮する
- (1)聞いて理解する力(聴解力)、読んで理解する力(読解力)の養成。
話し手・書き手の意図をくむ力を持つ。 - (2)伝達内容を明確にし、聞き手・読み手(年齢、立場)に合わせた話し方・書き方ができる力を持つ。
- (3)識字力を豊かにし、読むことを通して視野を広げ、未知の世界を知る。
- (4)発信する力、受信する力を養い、コミュニケーション能力を高める。
- 参考文献
- 文芸春秋 特別版 3月臨時増刊号: 言葉の力 ―生かそう日本語の底力― 「読む、書く、話す、聞く」全編書き下ろし95人の言葉の使い方 (2005)