おうしゅう市議会だより第29号
おうしゅう市議会だより第29号 6月定例会
サムネイル画像下のリンクをクリックするとページごとのPDFファイルを閲覧することができます。
表紙
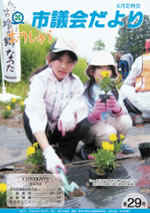
おうしゅう市議会だより第29号の表紙 (PDFファイル: 466.9KB)
CONTENTS 主な内容
- 6月定例会のあらまし 2ページ
- 一般質問 4ページ~11ページ
- 追跡調査 16ページ
- 私もひとこと 18ページ
- 発行日/ 平成25年7月25日
- 発行/ 奥州市議会
- 編集/ 奥州市議会広報編集委員会
定例会後 年4回発行
2ページ

おうしゅう市議会だより第29号 2ページ (PDFファイル: 516.9KB)
成人風しん 予防接種助成 追加補正
1人につき 3,000円助成
6月定例会のあらまし
平成25年第2回定例会は6月7日から24日まで18日間の会期で開催し、報告17件、諮問2件、議案29件が提案されました。
また、一般質問には議員16名が登壇し、市長及び教育委員長等の考えを質しました。
議案審議では、成人を対象に風しん予防接種費用の一部を助成する経費等を盛り込んだ平成25年度一般会計補正予算をはじめ、条例の制定や一部改正等を審議し、いずれも原案通り可決しました。
常任委員会に付託した請願2件、及び継続審査となっていた請願2件、陳情1件は、「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願」、「公的年金2.5%削減中止の意見書提出を求める請願」を採択、「各区地域包括支援センターの人員配置を充実させ、業務の市役所本庁への集約の中止を求める陳情」を不採択としました。また、「バス交通計画についての請願」、及び前回3月定例会で特別委員会を設置した「県南広域振興局誘致についての請願」は引き続き継続審査としました。
補正予算の審議
2千717万2千円を追加補正
質問
風しん予防接種の対象年齢・周知方法・助成期間は。
答弁
対象者は19歳~23歳までの麻疹・風しんの2種混合未接種者813人・24歳~49歳までは全員で35,099人である。助成額は1人につき3000円である。周知方法は個別通知と事業所等にも予防対策の周知を図っていく。期間は10月までとしているが、接種率等をみながら延長も考えていく。
協働のまちづくり交付金は継続
質問
協働のまちづくり交付金の執行状況はどうか。先進事例の事例発表会の機会を設けるべきと思う。また交付金は平成27年度までとなっているが継続するのか。
答弁
執行状況は平成23年度53%、平成24年度70.3%となっている。まちづくりフォーラムを開催し先進事例発表、意見交換等をしてきた。今後も継続して開催していきたい。交付金制度は自立、協働で地域自治を実践していく事が重要と考えている。制度内容は検討するが、交付金は継続する。
3ページ

おうしゅう市議会だより第29号 3ページ (PDFファイル: 526.5KB)
条例の制定等
州市子ども・子育て会議条例を制定
今年度はニーズ調査・支援事業の検討など
平成24年8月に公布された子ども・子育て支援法に基づき、市では「子ども・子育て会議」を設置し、子ども・子育て支援事業計画の策定や、地域型保育事業者の認可、給付対象施設の確認等のための基準整備などにあたり子育て当事者の意見を聞くことを目的とし本条例を制定しました。
質問
この条例の趣旨は待機児童を解消し、健やかな子育てをするための支援制度を検討する会議の条例である。会議のメンバーはどのような構成か。任期は何年か。子育て支援制度を制定するスケジュールは。
答弁
メンバーは子育ての当事者(保護者)を入れた構成にする。任期は2年である。この制度は平成27年度から制度が創設されるが、平成25年8月までに子ども・子育て会議を開催、9月から12月にニーズ調査を実施し、支援事業の需要の中身を踏まえて、平成26年4月から6月に関係施設(保育所、幼稚園)と協議し、26年9月を目途に条例を制定する。
質問
待機者をなくすことに主眼を置き、保育所等施設の安全基準をおろそかにすべきでないと考えるが。
答弁
ワーキンググループ等を組織し現場の意見を聞きながら、安全基準を最重要視し計画を策定していく。
老朽化した市営住宅を廃止
奥州市市営住宅管理条例の一部改正
入居者の生活水準及び安全を十分に確保することができなくなる恐れがある市営住宅を廃止しました。(瀬原第1団地)
前沢北部地区農業集落排水事業が完了
奥州市農業集落排水事業分担金条例の一部改正
事業完了に伴い、新たに受益者となる者に係る分担金を定めました。
人権擁護委員の推薦
平成25年9月30日をもって任期満了となる人権擁護委員の後任候補者を全会一致で推薦しました。
事業完了に伴い、新たに受益者となる者に係る分担金を定めました。
- 荒川 史子(あらかわ ふみこ)氏
(水沢区)新任 - 菊地 則子(きくち のりこ)氏
(江刺区)再任
4ページ

おうしゅう市議会だより第29号 4ページ (PDFファイル: 478.6KB)
ここが聞きたい一般質問
今定例会の一般質問は、16人の議員が登壇し、行政運営について市長及び教育委員長等の考えを質しました。質問、答弁の要旨を掲載します。(文責は質問議員)
佐藤郁夫
- 国際リニアコライダー(ILC)の誘致活動は
- ニホンジカ・ハクビシンの被害対策は
質問
国際リニアコライダー(ILC)国内候補地(北上山地・脊振山地)の一本化が今夏とされている。現時点での状況は。また、岩手県・奥州市の取り組み状況は。
市長
ILCの国内候補地一本化に向けた状況は、国内の研究者グループが公平な評価を行うため、両候補地に立地技術評価項目、社会基盤評価項目について資料の提出を求め、現在提出された資料を基に地質などの科学的な観点と、研究者などの居住環境などの社会基盤の観点から総合的な評価を行っている。学術的な評価結果は七月下旬に公表される見込みであるが、地質などは北上山地が優れていると思っている。東北ILC推進協議会を推進母体として北海道、新潟県を含め東北が一体となって北上山地を国内候補地とするよう要望活動を展開している。奥州市独自の取り組みとしてはILC特設サイトの設置、リーフレット、ポスターの作成、広報おうしゅうへの特集記事の掲載など市民理解の醸成を図っている。また、いわてILC加速器科学推進会議が中高生向けの副読本を作成し、誘致機運を高めるなど、関係者一体となって誘致活動を展開している。
質問
近年ニホンジカ・ハクビシンによる農作物の被害が多くなっているが被害の実態は。また被害対策として胆江農業共済組合では電気柵購入費の助成制度を創設したが、市の被害対策は。
市長
被害の実態は把握していない。ハクビシンは捕獲ワナ100基を購入し無償貸し出しをしている。ニホンジカは柵の設置か捕獲しかないと思うが、行政機関、農林業団体、猟友会で構成する奥州市鳥獣被害対策協議会で被害実態の把握と対策を検討していく。
5ページ

おうしゅう市議会だより第29号 5ページ (PDFファイル: 503.9KB)
関笙子
- 統合前沢小学校開校までに通学路の安全対策を
- 認知症対策を急いで
質問
通学路における事件・事故の発生は食い止めなければならない。来春開校する統合前沢小学校児童700名のほとんどの通学路が変わる。下校時日没の早い時期に防犯灯等のない道を帰る児童もいる。平成22年度より関係者で組織されている検討委員会から要望書が出されている。開校まで実現してほしい。現在までどの様に検討されているか。
市長
要望書に添った検討を行っている。関係団体や警察・公安委員会等に内容を伝えながら年度内に実現する様努めている。さらに現在スクールガード1710名、子供110番の家800カ所を含め、市民の皆様の協力を得ながら通学路の安全確保に努めている。これからも事件・事故防止に向け万全を期して行く。
質問
奥州市の高齢化率が30%を超えた。認知症の進行やそれに伴う様々の課題が出て来ており対策が急がれる。介護保険料の引き上げ等により軽度の要支援1と2を分離して市の対応に移管する動きがある。また財産等の管理や相続について裁判に巻き込まれている市民も出て来ていると聞く。対策が急務と思うが。
市長
現在要支援1と2の軽度の対象者は1771人いる。市独自の対策を急ぐ必要に迫られている。また相続問題等も出て来ている実態もある。後見人制度の取扱いも行っているが今まで相談に訪れたのは9件に止まっている。認知症が進んでからの相談が多く解決がむずかしくなっている例もある。早目に相談に来て頂くよう周知する等、老後を安心して暮らせる環境の整備を急いで整えたい。
飯坂一也
- 空き家等の適正管理条例の制定を
- 青年世代の市政への参画を
質問
適正に管理されていない空き家が増える傾向にある。所有者の管理や地域の見守りが大事であるが、行政でなければ対応できない様々な問題も起きている。条例を制定し、具体的な対策が打てるようにすべきと考えるが。
市長
条例の制定については、導入した県内自治体の適用事例等を参考としながら、実効性を含め検討したい。
質問
不良住宅の除却に関し、国からの支援を受ける制度が今年度から始まっている。市としてどのように考えるか。
市長
この事業は、個人の所有権などの調整や市の財政的な負担も大きいことなど、慎重な検討が必要と考える。
質問
空き家対策は、税務や建築・環境・消防・防犯・跡地活用など問題が多岐に渡る。部署間の連携が必要と考えるが。
市長
現状を基礎としながらも、部署間の連携を強く意識しながら適切な対応に努めていく。
質問
職場や家庭において、様々な問題や悩みを抱えている青年世代の声を吸い上げるしくみが必要ではないか。市として意識調査などを実施すべきと考えるが。
市長
青年世代の意識の把握については、紙によるアンケートだけでなく、パソコンや携帯端末などを用いたフェイスブックなどを含め有効な手法を検討する。
質問
審議会などに青年世代枠を設けることについてどう考えるか。
市長
青年世代に向けた積極的な公募委員の募集や、青年会議所・PTA等、青年世代を中心に構成される団体への推薦依頼を意識していきたい。
6ページ

おうしゅう市議会だより第29号 6ページ (PDFファイル: 611.2KB)
菅原明
- 衣川診療所・前沢診療所の無床化の根拠は
- 衣川総合支所建設を早急に
- 前沢小学校統合に係わる課題策を
質問
衣川・前沢診療所の無床化案が、本年度中の策定を目指す、市立病院・診療所改革プランのたたき台で示されたが、無床化にする根拠は何か。5月に開催された市政懇談会で報告しなかったのはなぜか。市長は両診療所を今後、どのようにしようとしているか。
市長
このままでは市の医療体制が崩壊してしまうという危機感を持っている。前沢・衣川診療所は19床ずつで、現在、前沢は常勤医師1人、衣川が常勤医師と臨時医師各1人が入院診療を担っている状況だが、休床化で外来診療など、一次医療施設としての機能を充実させていきたい。
質問
衣川区の総合支所建設について、衣川地域協議会との協議を重ね、早期の建設を進めるべきではないか。
市長
地元住民の意向を尊重することが重要であり、住民の意向集約、世論の形成を見極めた上で進めて行きたい。総合支所の整備は衣川のまちづくりに密接に関係するので、限られた財源の中でより良いものになるよう話し合い、速やかに実現を目指したい。
質問
平成26年4月から前沢統合小学校がスタートするが、放課後の児童の居場所づくり、スクールバスの運行計画と、バスの確保についてどのように検討しているか。
市長
放課後は、子ども達を地域に帰すことを基本として開設に向け準備を行なっている。統合後、放課後児童の居場所の利用希望調査を行なったところ、約350名の希望があった。放課後の学校から各施設までは、スクールバスによる移動を考えている。現時点で設置されていない地域についても、今後、利用希望調査を行ないながら、地元と協議を進めていく。
教育委員長
スクールバスの運行については、6台のバスを運行し、8コースを予定している。試乗調査をかさね、特にも、低学年の子供達に配慮する形で検討していく。
阿部加代子
- リサイクル推進(小型家電リサイクル、資源ゴミ回収)を
- 胃がん検診(ピロリ菌感染へのリスク検診)の充実を
質問
本年4月より小型家電リサイクル法が施行となったが、自治体の取組みは任意となっている。当市の取組み状況は。
市長
認定業者が決まっておらず、回収品の買取り金額も判明していない状況であり、回収や保管に要する費用、運搬費用など、国の補助内容が示されていないことで現時点では整備されていないが、国の動向を見極めながら適切に対応していく。
質問
民間のスーパー等でも資源ゴミ回収に取組んでいる。買った所へ戻すという意識を持ち、市のリサイクル費用の削減を目指すべきではないか。
市長
市民、行政、民間事業者がそれぞれ役割を果たし、環境保全のパートナーとしてリサイクル、ゴミの減量化を推進したい。
質問
胃がんは毎年11万人が発症し約5万人が死亡している。胃がんの大きな原因はピロリ菌であり、今年の2月からピロリ菌を除去する薬の保険適応範囲が、慢性胃炎にまで拡大され胃がん予防が大きく前進すると期待される。血液検査でピロリ菌感染についてリスク判定を行う検査を導入する自治体が増えて来た。リスク検診導入の考えは。
市長
胃がんの死亡率は当市は男女共全国、県よりも高く早期発見のため検診受診率の向上が課題である。胃がん検診のあり方として従来の検診に加え、リスク検診の併用の有効性、実施に向けての課題の検討を行う。市民が安心して受けられる検診として検討を図る。
7ページ

おうしゅう市議会だより第29号 7ページ (PDFファイル: 510.8KB)
遠藤敏
- 農業後継者どう育てるか
- 鳥獣被害にどう対応する
質問
奥州市は豊かな自然と豊穣の土地をもち、米をはじめ多くの農産物を産している。高齢化が進みつつあるこの産地を守り育てるための後継者対策の取り組みとその成果は。
市長
胆江地方農業振興協議会では、新規就農希望者への総合的な就農相談活動、受け入れ態勢の整備、営農指導を行い、平成22年度11名、23年度17名の定着を確認している。
質問
関係団体による後継者相談室を立ち上げ、さらに積極的に現場に出向いて相談に当たる体制が必要でないか。
市長
どの窓口に相談があっても就農相談カードで情報共有できる形となっている。今の体制をさらに充実する。
質問
鳥獣被害の実態はどうか。
市長
平成24年の人的被害はツキノワグマによる被害が2件、重症1名、軽症1名。農作物被害はツキノワグマによるもの13件、ニホンジカ、ハクビシンは全容を把握していない。
質問
対策を立てるには被害の実態をつかむ必要がある。鳥獣被害防止計画の対象鳥獣に非常に凶暴と言われているイノシシが入っていないのはなぜか。
市長
今後被害の届出の周知をしていく。イノシシについては県と協議し検討していく。
質問
猟友会の役割は非常に大きく、どう連携していくか。その活動を市民に知らせることも大事でないか。
市長
組織の活性化に向けて猟友会との話し合いを進めていく。猟友会の活動を広報等での紹介については検討したい。
加藤清
- TPP交渉参加による地域経済の影響は
- 農業の6次産業化推進の考えは
質問
環太平洋経済連携協定(TPP)交渉により、本市の農業と地域経済に甚大な影響を及ぼすことが予測されるが、その対策は。国・県に、施策の転換を強く求める必要があると思うが、市としての基本的な考え方は。
市長
基幹産業である農業、そして地域経済への影響は甚大であることが予測されることから、他団体と連携のもと、集落営農、法人化規模拡大、6次産業化等の支援を進める。さらには国が示している、強い農業施策方針等を活用し、新たな強い経営体育成に努める。国内議論をせずTPP交渉を進めることは受け入れられず、あらゆる場面を捉え、国に強く要請していく。
質問
農業振興を図る観点に於いて、6次産業化を進める必要があると思われる。その取り組みの考え方と、今後の課題、改善対策は。さらに地域農業マスタープラン策定は農業振興施策の根幹にかかわるものと考えるが、策定に於ける基本的方針は。
市長
6次産業化については、農産品の新たな販路開拓や拡大を行う農業者への支援を進める。さらには農業者ニーズに応えるため、補助金のあり方を含め事業の見直しを検討する。マスタープラン策定については、地域での協議を基に他団体と連携しつつ、本市の農業はどうあるべきかを含めより望ましいプランの策定を行う。
8ページ

おうしゅう市議会だより第29号 8ページ (PDFファイル: 505.1KB)
佐藤克夫
- 地域福祉の課題
- 学校家庭地域の連携
質問
地域福祉計画推進上の課題となっている点は何か。
市長
平成23年度に奥州市福祉計画を作成して以来、推進の基礎単位を各地区センターとし、地域ごとに福祉懇談会を重ね、一層安心・安全な地域づくりを目指している。地区センターと行政区との連携、民生委員や社会福祉協議会等との協働、高齢者・子どもの見守りを中心にした地域の支え合いづくりが課題となっている。
質問
高齢者の見守り体制の整備はどこまで進んでいるか。
市長
少子高齢化が一層進む中で、小地域ニコニコネットワーク、ご近所福祉スタッフ等の整備が進み、緊急連携カードの採用や見守り応援隊が整備される等、地域における高齢者見守り体制は整いつつある。
質問
市内における「学校支援地域本部活動」の推進状況はどうか。
教育委員長
市内の学校支援地域本部は、水沢中・水沢南中・東水沢中・江刺一中・小山中の5本部に設置され、それぞれの管内小中学校で組織されている。そして学習支援活動・読書活動への支援・部活動・登下校安全指導等が各地域教育協議会の計画のもとに実践されている。学社融合も教育振興運動として継続されている。
質問
放課後子ども活動で、課題となっていることは何か。
教育委員長
放課後活動は順調に推進されている。地域の協力関係がよく、指導者の確保も順調で、学校との連携もスムーズに推進されており、着実な放課後活動が展開されている。
藤田慶則
- 目指せ 国際研究都市 奥州市
- 創れ 市民栄誉賞
質問
市政懇談会で示した、ILCを核としたまちづくりにおいて、4つの項目の考えは。
市長
(1)地元の受け入れ意識の醸成は、研究者とその家族が地元に歓迎されていることが、大変重要で、地域に安心して溶け込めるよう、交流や連携の仕組み作りが必要となる。(2)多文化共生意識の涵養は、外国人住民も共に地域社会を支える主体であるという認識を持つことが大切である。(3)住居・教育・医療などの受け入れ体制の充実は、住宅・子弟の教育場所、医療機関の確保が、重要な課題であり、県や関係機関などと連携を図り、取り組んでいきたい。(4)研究者の家族支援は、外国語でのサポート体制の構築は不可欠であり、ワンストップサービスや生活サポート体制の整備などが必要。また、医療や教育などのインフラの整備とともに、観光・レジャー施設の整備、配偶者の就労の場の確保についても重要な課題とされる。
質問
小学生の英語学習の現状は。
教育委員長
第5・6学年において、外国人講師を活用し、週1回程度、年間35時間を目安に外国語活動の授業を実施している。その中で、国際社会に関心をもち、英語に親しむ環境づくりができるものと考える。
質問
市民栄誉賞を創設する考えはないか。
市長
現在奥州市名誉市民条例は制定されている。将来、候補者が輩出された際には、既存条例を踏まえ、内外にその功績を示すことができる表彰の方法を検討する。
9ページ

おうしゅう市議会だより第29号 9ページ (PDFファイル: 478.7KB)
高橋政一
- 教育再生実行会議に対する見解を問う
- 市有林の状況とその活用は
質問
安倍首相は教育再生実行会議(以下、会議という)を開催し、教育改革を推進するとしている。会議が出した「教育委員会制度等のあり方について」の提言では、教育委員長と教育長の責任の所在が不明確、教育委員会の抜本的改革が必要、市町村単位での人事異動、教育長や教育長候補を特定し研修を行うなど、その内容に問題があると考えるが見解を問う。
教育委員長
教育長は事務方で、教育委員長が中心になって教育委員会議を主催しており、役割分担はしっかり行われている。教育委員会制度は政治からの中立などさまざま加味した制度であり、改革は多方面にわたって意見を聞きながら、拙速な進め方は禍根を残す可能性がある。市町村単位での人事異動については、大都市の発想で、岩手県は教育出身者が偏っているので、全県交流人事をしている。教育長候補者を特定しての研修は現実的でない。
質問
奥州市の森林面積は市の総面積の59.8%を占めている。奥州市の森林は膨大な森林資源である。市有林の整備状況と市産材の活用状況について伺う。
市長
国県の補助を活用し除間伐を行うとともに、伐採適齢期を超えた事業区については順次立木を売り払っている。市の公共施設について、地元産木材の積極的な利用に取り組んでおり、小学校の校舎や地区センターの新築工事で可能な限り市産材を使用している。
佐藤邦夫
総合支所と地区センターの役割
質問
基礎自治体の規模、能力を充実し、行財政基盤を強化するとのことで、国は市町村合併を推進してきた。胆江は一つということで、合併を推進してきたが、「合併して何も良いことはない」、「合併しなければよかった」との市民の声が聞こえる。一方「競馬」「水沢病院」、「土地開発公社」の問題解決への取組みは合併効果と考えるが市長の考えは。
合併後の旧5市町村の一体化、合併して良かったと思ってもらえるには、各総合支所が元気になることが必要だと思うが。
市長
合併したことに賛否の声はあるが、合併の効果は確実にある。岩手競馬、水沢病院、土地開発公社の問題は合併し財政規模が大きくなり、着実によりよい方向に向かっている。各総合支所は各地区センターを十分に指導し、地区民に不便をかけないような組織づくりをする。
質問
各省庁では補助率100%や50%の事業が多くあり、その多くは公募している。私どもは一昨年500万円あまりの予算を頂き、金ケ崎を含む産直が協力して津波の被災地に毎月野菜を届ける事業をした。しかし事務の煩雑さや多さから苦労した。そこで役所が集中的に予算を探し、事務的援助をする部門を設けてはどうか。市内の団体、NPOや各振興会などに事業実施してもらうと地区の活性化や人材育成にもつながると考えるが。
市長
役所内に専門部署を作るかどうかは別にして、各地区振興会が事業を担うという考えは、今後検討してみたい。
10ページ

おうしゅう市議会だより第29号 10ページ (PDFファイル: 502.3KB)
小野寺重
- 農業マスタープランの推進方策は
- 「人口減少対策」移住促進事業の課題は
質問
農政は毎年のように変り迷走するとも受けとめている。現場ではさまざまな戸惑いがおきている。担い手不足、高齢化等の状況からリタイヤする農家が続出する危機的状況であり、人・農地プラン作りを急ぐべきである。特にも基盤整備未実施地区、中山間地域の取り組みを行政、JAが連携し強力に推進すべきと考えるが。
市長
我国の食と農林漁業再生のため、持続可能な力強い農業実現のため、地域農業マスタープランを作成する。高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加など、全国的に農業農村が抱える人と農地の問題に地区集会、座談会に出向くなど関係機関と連携のうえ引き続き対応していく。
質問
奥州市の人口は平成24年度、出生が869人、死亡が1,587人で718人の減、転出入の差264人減で全体として982人の減である。人口の増減はまちのバロメーターである。人口減少の理由のひとつに、働く場所がないなどがある。住み良いまちづくりをして人口減少をくいとめなければならない。移住促進事業、空き家バンク事業の現状と課題はなにか。
市長
人口減少の実態は死亡が増加、出生が減少、進学や就職による若者の流出、未婚率の上昇や景気の低迷による就職難などが要因と考える。子育て環境整備、雇用の場確保に積極的に取り組む。空き家バンク事業は66件で136人が移住している。希望が多く空き家の確保が課題で掘り起しに努める。
及川善男
国の臨時経済対策に伴う国庫補助金等を活用し、地元経済の活性化と教育環境整備などの対応を行なうべき
質問
国は臨時経済対策として、奥州市に対し国庫補助事業分26億3千万円余、元気交付金12億9千万円余を配分した。この財源を、疲弊している地域経済の活性化や住民福祉の向上、教育環境整備などに活用するとともに、浮いた財源などで(1)江刺区玉里小学校の危険校舎改修、(2)水沢南中学校大規模改修を北校舎だけでなく中央校舎も対象に、(3)胆沢区のスクールバスにエアコン設置などを行なうべきではないか。
市長
玉里小学校、水沢南中学校、スクールバスの状況が、思わしい状況でないことは知っている。遅きに失したということの無いよう、どのような対応ができるか、突っ込んだ検討をしたい。
質問
国庫補助事業分のうち19億9千万円は舗装修繕工事であり、等級別発注件数は特A級10件、A級21件、B級2件、C級1件である。市の請負資格者のうち、1億円以上の特A級業者は市内にはいない。(表参照)これでは、19億9千万円の事業のうち、10億円以上が市外の特A業者に発注されることになる。共同企業体方式の採用や請負工事費限度額の見直しなどを行い、市内の多くの業者がこれらの事業に参画できるようにすべきではないか。
市長
設計額が1億円を超える工事は、市内の複数業者による特定共同企業体を構成して発注するなど、市内の多くの業者が参加できる仕組みを考える。
11ページ

おうしゅう市議会だより第29号 11ページ (PDFファイル: 467.3KB)
千田美津子
市内 小・中学校の老朽化が著しく、道路整備が1・2年遅れても、学校整備を優先すべきでは
質問
共産党市議団として、市内45の小・中学校のうち44校を訪問した。多くの学校が老朽化のため、修繕を必要とする箇所が多数あるがそのまま放置されている。
昇降口のタイルが大量にはがれている学校、パソコン教室や図書室が雨漏りしている学校、体育館への通路が腐食し雪が吹き込む学校、遊具が壊れ「危険」の張り紙がなされたままの学校も数校、その他にも挙げたら切りがないほどで、子どもたちの環境としては悲惨な状況だ。
市政課題は多いが、たとえ道路の新設改良が1・2年遅れたとしても、学校の修繕費を増額し、子どもたちの環境を改善すべきではないか。また、学校の整備計画を早急に策定すべきだ。
市長
建物や設備の老朽化により、修理や改修工事を必要とする経費は年々増えている。児童・生徒が安全で安心して学校生活が送れるよう、計画的な環境改善を進めたい。学校の整備計画については、課題としてとらえており、学校の適正規模、各地域の諸課題や児童・生徒数の状況等により、望ましい整備のあり方について検討していきたい。
質問
いじめ問題等への対応のため、スクールカウンセラーと養護教諭の配置については、現場の声にこたえて充実配置すべきではないか。
教育委員長
スクールカウンセラーと養護教諭の配置については、今後も学校の希望や実態等を把握しながら、県教育委員会と連携し進めたい。
千葉悟郎
「協働のまちづくり」の進捗状況は
質問
市長の最重要政策の協働のまちづくりが、まちづくり交付金を導入して3年目になるが、この「交付金」の活用によって、各区の協働のまちづくりにどのような効用があったのか、その評価を聞きたい。
市長
「交付金」事業の中間年としての実施評価は、平成23年度と24年度の「交付金」活用を比較して、24年度は、313事業、執行額1億2千221万9千円、執行率70.3%と、24年度は事業数、執行額ともに23年度に比較し、約2倍の増加となった。これは、23年度が初年度ということもあり、地域コミュニティー計画の見直しに時間を要したが、24年度は速やかな合意形成で事業実施が着実に進んだものと評価している。
質問
協働のまちづくり政策に対する住民の意識の低さやリーダー不足が各区にあると、市のヒアリング調査で指摘されている。
この政策の基本は地域住民が地域課題や問題を取り上げ話し合って、その解決の糸口を見つけるために自ら行動することである。そのためには市職員が、まず市長の政策「協働のまちづくり」の理念と手法を理解することと、協働のまちづくりアカデミー研修会に参加し、各区において啓発的役割を担うことで政策の浸透が図られるとして市長に提案したい。
市長
地区センターに市職員を配置して、その任にあたっている。さらにはまちづくり交付金が「協働のまちづくり」の作業工程のなかで、地域の人たちが自分たちの地域の問題を解決する契機になってほしい。
12ページ

おうしゅう市議会だより第29号 12ページ (PDFファイル: 655.7KB)
今野裕文
前沢・衣川診療所無床化の撤回を
質問
水沢病院の経営改善に向け病院特例債借入れの際、策定された「奥州市立病院改革プラン」で、計画未達成になっているのは、病院会計の統一と診療所の機能の明確化である。今度策定される「奥州市立病院・診療所改革プラン」では、病院・診療所の会計の一本化と、前沢・衣川診療所の廃止を平成27年4月から実施する計画である。この計画を進めることは、今ある病院・診療所の体制さえ壊しかねない。地域づくりにとって重大な問題である。この計画を撤回し時間をかけて地域住民を巻き込んだ議論をすべきでないか。
市長
今の医療の状況は医師・看護師等の献身的な努力で成り立っている。このような状況で果たして5年後・10年後、もつのかと大いに心配がある。
5年後の市立施設の医師の平均年令を考えると背筋が凍り付く状況である。根本的な仕組みをかえなければ、医師・看護師などの確保は難しくなると考えている。それほど時間が残っていないと受け止めている。
質問
現在の計画で未達成になっている会計の統一、診療所の入院ベットの休止を盛り込まなければならないのか。
市長
今度策定する計画は、国や県に策定を求められているものではない。従って会計の統一や診療所の無床化を求められていない。また、いつまで策定しなければならないともされていない。
請願等の審査内容
6月定例会において付託のあった下記の請願について、所管常任委員会及び特別委員会で審査しました。審査結果は次のとおりです。
なお、請願第40号については、本会議において審査結果とは異なる結論に至りました。
- 番号 請願第36号平成24年12月、25年3月定例会で継続審査
- 請願名 バス交通計画についての請願
- 請願者 奥州市胆沢区小山字弁天堤下3-22
小野寺 勉 ほか1名 - 審査内容 内容をさらに精査し、現状との比較やその実行性についても検討をした上で判断すべきとの観点から、再度継続審査。
- 審査結果 継続審査
- 所管委員会名 総務常任委員会
- 番号 陳情第34号平成25年3月定例会において継続審査
- 請願名 各区地域包括支援センターの人員配置を充実させ、業務の市役所本庁への集約の中止を求める陳情
- 請願者 奥州市胆沢区若柳字化粧野146番地
阿部 一江 - 審査内容 この4月より地域包括支援センターの人材が本庁へ集約され3カ月弱となりますが、現在、各種情報の共有等を図りながら本庁と各支所との連携を密にし、さまざまな困難事例に対応できる体制が強化されているとの観点から、不採択。
- 審査結果 不採択
- 所管委員会名 教育厚生常任委員会
- 番号 請願第39号
- 請願名 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願
- 請願者 盛岡市本町通2-1-36 浅沼ビル5階
岩手県医療労働組合連合会 執行委員長 中野るみ子 - 審査内容 高齢化社会や長寿命化社会に向けて医師、看護師等に係る負担はますます増える一方、医療、福祉労働者の人手不足が深刻であり、夜勤、交替制労働者等の勤務環境改善は喫緊の課題であることから、必要な人材の確保を図り、安全、安心の医療介護実現のためにも法規制などの労働環境改善が図られる施策を講じる必要があるとの観点から、採択。
- 審査結果 採択
- 所管委員会名 教育厚生常任委員会
- 番号 請願第40号
- 請願名 公的年金2.5%削減中止の意見書提出を求める請願
- 請願者 盛岡市本町通2-1-36 浅沼ビル6階
全日本年金者組合 岩手県本部 執行委員長 小松原 進 ほか1名 - 審査内容 現在年金財政の置かれている立場は厳しい状態にある中、年金額を本来の水準に引き下げる手立てを取るべきであり、またこれから支払わなければならない人たちのためにも、どうしてもやっておかなければならないことであり、年金削減中止の意見書を提出すべきでないとの観点から、不採択
- 審査結果 不採択 本会議において採択
- 所管委員会名 建設環境常任委員会
- 番号 請願第38号平成25年3月定例会において継続審査
- 請願名 岩手県南広域振興局の誘致についての請願
- 請願者 奥州市江刺区大通り1-61
江刺地区振興会長連絡協議会 会長 廣野 雅喜 ほか1名 - 審査内容 振興局の移転は奥州市民にとっても大きな課題であるとともに、近隣市町村への影響も大きいと思われることから、更に継続して調査すべきとの観点から、継続審査
- 審査結果 継続審査
- 所管委員会名 岩手県南広域振興局の誘致についての請願審査特別委員会
13ページ

おうしゅう市議会だより第29号 13ページ (PDFファイル: 844.9KB)
賛否の公表
(注意)採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。これ以外の案件は全会一致で可決等されています。
陳情第34号 各区地域包括支援センターの人員配置を充実させ、業務の市役所本庁への集約の中止を求める陳情【教育厚生常任委員会の審査結果[不採択]に対する討論】
- 反対討論
介護保険関係法律は、65歳以上の高齢者3千人から6千人毎に保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員を最低限それぞれ1人配置することとされている。人員の配置を充実させ困難事例に対応するため市全体の事業計画を取り仕切る部署を設置し対応するのが法の趣旨に求められるものと考える。各区の包括支援センターを充実させることが求められていると考えられ、原案に賛成し委員長報告に反対する。 - 賛成討論
地域包括支援センターの人材は4月より本庁に集約をされており、3か月ほど経過しているが困難事例に対しても本庁と支所がよく連携されており、大変丁寧に対応している。さまざまな情報の共有を図りながら運営されており、現状の有資格の人材をフル活用し連携強化が図られていることから原案に反対し委員長報告に賛成する。
請願第39号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願
- 反対討論
奥州市においては規定の労働時間は守られており、夜勤の勤務時間の間隔は12時間以上確保されている。疲労回復に十分な時間間隔を開けることは、個人差もあり客観的である。医師、看護師、介護職員の大幅増員は理想であるが大変困難である。請願の趣旨は理解できるが妥当性、実現性を欠くと判断し、委員長報告に反対する。 - 賛成討論
昨年、岩手県内にあるNPO法人岩手地域総合研究所が実施した震災後の仕事と暮らしに関する調査が行われ、医療職の方々の声として、65.5%が大変な心労の疲労を第一に掲げられている。特に職員増や改善策を望む声が圧倒的に多かった。被災地である岩手県内全体を考えるべきである。夜勤や交替制労働者の増員と労働環境の改善のため、法整備が必要だとするこの請願は被災県として震災からの復興、地域医療の再生の願いはまさに当然のことであり委員長報告に賛成する。
請願第40号 公的年金2.5%削減中止の意見書提出を求める請願【建設環境常任委員会の審査結果[不採択]に対する討論】
- 反対討論
物価が下がっても生活必需品は上がっている中、高齢者生活は税金や保険料などが年々上昇し年金の手取り額が少なくなるのが実情である。政府は2.5%削減したあと、毎年0.9%程度の年金引下げを続ける方向で検討している。当市議会は昨年6月に同様の請願を採択し、意見書も提出していることから原案に賛成し委員長報告に反対する。 - 賛成討論
年金財政が厳しいことは全国民が認識しており、年金がこのまま継続するということは非常に難しい状態である。若い人たちは国民年金等を納めていない方も随分多い状態で、将来的に年金が行き詰まるということは分かっている。年金は物価スライドが原則でルール上であれば、きちんとやるべきという観点から、原案に反対し委員長報告に賛成する。
14ページ

おうしゅう市議会だより第29号 14ページ (PDFファイル: 760.9KB)
特別委員会報告
競馬事業調査特別委員会
6月21日の委員会では、市長はじめ担当職員のほか、岩手県競馬組合から常勤副管理者等が出席し「平成25年度の岩手競馬事業計画について」「現在までの開催状況について」「平成24年度決算見込みについて」を調査しました。
平成25年度は「岩手競馬の魅力向上」「購買環境の整備」「強固な経営体質の構築」の3つを基本方針に掲げて取組みを推進し、4月6日から6月10日までの30日間における岩手競馬発売額の計画達成率は119.1%で、自場発売、広域委託発売、インターネット発売ともに計画を上回っている状況にあります。
平成24年度の決算見込みは、当初の計画を10億円程度上回り182億5500万円となり、必要な施設整備と資金確保を行いながら8700万円の当期利益を確保することができる見通しとなり、この当期利益は平成27年度からの地方競馬全国協会1号交付金の償還に備えて財政調整基金に積立てを行ったとのことでした。
東日本大震災調査特別委員会
4月17日の委員会では、市長はじめ担当職員の出席のもと「出荷制限等の対象となっている野生山菜類の放射性物質濃度調査の実施について」調査しました。
6月20日の委員会では(1)共同仮置場設置の進捗状況について(2)農林業系副産物焼却処理等円滑化事業に係る前処理施設設置の進捗状況について(3)市内産農産物の放射性物質測定の基準値及び測定結果について(4)放射線内部被ばく健康調査の結果について調査しました。
共同仮置場設置については、説明会を開催するも一部反対意見があり住民合意に達した地区はなく、今後も安全性の説明に重点を置き推進することとしています。また、放射線内部被ばく健康調査(尿採取)の結果については、2名の専門家の評価は「放射性セシウムによる健康影響は極めて小さいと考えられる」とされているが、引き続き調査が必要ではないかという意見が出されました。
また、6月28日に福島市「除染情報プラザ」において除染の必要性、除染の効果、仮置場について研修を行いました。
議員発議
議員発議により下記2件の意見書を可決しました。そのうち1つの意見書を掲載します。
- 安全・安心の医療と介護実現のための夜勤改善及び大幅増員を求める意見書
- 公的年金2.5%の引き下げに反対する意見書
安全・安心の医療と介護実現のための夜勤改善及び大幅増員を求める意見書
東日本大震災では、「医療崩壊」「介護崩壊」の実情が改めて明らかになり、その中で医師、看護師、介護職員など医療・福祉労働者の人手不足も浮き彫りになりました。
厚生労働省が平成23年6月17日に出した「看護師等の『雇用の質』の向上のための取り組みについての通知(5局長通知)では、「看護師等の勤務環境の改善なくして、持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めない。夜勤・交替制労働者等の勤務環境改善は、喫緊の課題」としています。安全・安心の医療と介護実現のためにも、看護師など夜勤・交替制労働者の増員と労働環境の改善のために法規制が必要です。
震災からの復興、地域医療再生のためにも、医療及び社会保障予算を先進国並みに増やし、国民の負担を減らすことが求められています。
医師、看護師、介護職員等の増員を実現し、安全でゆきとどいた医療・看護・介護の拡充を図るための対策を講じられるよう、下記の事項について強く要望いたします。
記
- 看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を、1日8時間、週32時間、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること。
- 医師・看護師・介護職員等などを大幅に増やすこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成25年6月24日
岩手県奥州市議会
提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、岩手県知事
15ページ

おうしゅう市議会だより第29号 15ページ (PDFファイル: 832.8KB)
議会広報編集委員会行政視察報告
- 視察日
平成25年5月13日~14日 - 視察先
- 全国市議会議長会
- 東京都あきる野市
【全国市議会議長会】全国の議会だよりの特徴的な事例
川崎市の「議会カレンダー」、延岡市の「5分でわかる議会のしくみ」浦添市の「議会活動この1年」など、イラストや数字を用い、議会活動の1年の流れが分かり易く表現しておりました。全国の議会だよりを直接見ることができ、色の使い方、独自イラストの多用化や、インパクトのある表紙写真や題字の工夫など、大変参考となる内容でありました。
【あきる野市議会】議会だよりリニューアルに向けた取り組み
リニューアルに向け議員3名、職員1名による編集委員会を組織し検討に着手、市民アンケート等を実施しました。リニューアルの到達点は「議会だよりを見る市民を増やすため、手に取ってもらえる表紙づくり」「気づきを与える表現方法や読みやすさの工夫」とし検討を行いました。またデザイナーによるアドバイスとして、(1)導線(2)ホワイトスペース(3)統一感があげられておりました。また特集を組むことによりターゲットを絞ることも大事であるとのことで、表紙写真と次面の特集がリンクしているという紙面構成となっておりました。
今回の視察をとおし、議会広報のスタイルやデザインは、日々進化することを認識し、住民にとって簡単で分かりやすい紙面にする気持ちで編集することが大切であると強く感じてまいりました。
総務常任委員会行政視察報告
- 視察日
平成25年5月21日~23日 - 視察先
- 埼玉県富士見市
- 東京都日野市
- 静岡県富士宮市
【富士見市】市民判定人方式による事業仕分けの実施について
現市長のマニフェストに基づき、平成21年度と23年度に「無作為抽出による市民判定人による事業仕分け」を実施しています。事業仕分けは、コーディネーター1人、仕分け人5人、市民判定人10数人という体制で行われ、担当課による概要説明、仕分け人による質疑・議論、市民判定人が挙手により判定、コーディネーターからの判定結果発表、市民判定人1~2名からコメントという順序で進められます。
事業の評価としては、市民判定人の9割が事業仕分けに参加してよかったと回答しており、事業仕分けの目的である、市民との情報共有や行財政改革の推進はある程度達成できたとのことでしたが、その反面、判定が仕分人の考え方に大きく影響されるため、行政運営上廃止できないものが廃止の判定を受けたり、仕分けを行う事業の選択が難しいなどの問題点もあり、今年度の実施については検討中とのことでした。
【日野市】土地活用推進事業について
平成21年4月1日に土地活用推進室という組織を新設し、それまで土地の売却に関してバラバラだった組織をひとつにし、土地の売却と活用を専門に行っています。
公用車すべてに「日野市が土地を売っています」というマグネットシートを貼付することから始まり、住宅展示場でのキャンペーン、新聞折込みとポスティング、市内イベント等でのブース出店など、さまざまな形でのPR活動を行いました。
また、職員は、「公務員の殻を破り、民間の不動産業者と渡り合える位の知識を身につける」との市長の指示のもと、業務の役割分担を明確にするとともに、専用の携帯電話による土曜日、日曜日の対応もしておりました。
とにかく一箇所でも多く土地を売ろうという前向きな姿勢が強く感じられました。
【富士宮市】公共交通システムについて
利用者が少なく費用対効果が疑問視されていた民間バス路線を廃止し、病院や買い物などに利用できるよう、医療機関、集客施設、公共施設を循環する「宮バス」の運行を平成20年度から開始しました。
路線選定や運行形態の検討は、要望の強かった地域から選出した市民や交通事業者が参画しての調査会で行われましたが、調査会を何度も開催することにより、自分たちの公共交通は自分たちでつくるという意識が芽生え、自らアンケートの内容を考えたり、バス停オーナーの勧誘にも足を運ぶなど、市民参画による公共交通の確立が図られたとのことでした。
運行はタクシー業者に依頼し、セダン型のタクシーを利用、宮タクの業務以外は一般タクシー事業に使用できるものとしました。また、料金はバス並とし、ドア・ツー・ドアのサービス、完全予約制、途中下車禁止など、利用者と事業者双方に配慮した仕組みとなっておりました。
16ページ

おうしゅう市議会だより第29号 16ページ (PDFファイル: 393.0KB)
追跡調査 あれはどうなった
合併前の各区において進められてきた事業が現在どのように進捗しているか調査し、その状況についてお知らせします。
今回は、江刺区において事業推進している「南八日市新地野線整備事業」の内容を紹介します。
南八日市新地野線整備事業について
この路線は江刺中核工業団地及び江刺フロンティアパークの入口から南北に縦断する道路で工業団地に通勤する重要路線となっております。
江刺中核工業団地及び江刺フロンティアパークには現在52社が立地、従業員数は2,560人となっております。
工業団地へは東西南北から入る路線がありますが、南八日市新地野線は岩谷堂方面から入る路線で朝夕は大変な渋滞で、特に冬期間は路面が凍結し通勤に大変な支障が出ておりました。
旧江刺市時代から江刺中核工業団地企業協議会等から渋滞緩和の要望が出され、議会においても議論がされてきました。 平成24年3月議会において、江刺区振興会連絡協議会長から「江刺中核工業団地及び江刺フロンティアパークの交通渋滞緩和について」の請願が出され、採択されました。
請願採択を受け、市では平成24年、25年度の2ケ年事業で工事を施行しております。
工事内容は現在1車線の上り車線を片側2車線にし、凍結による渋滞も発生していることから上下線の一部に電熱線を埋め込む「ロードヒーティング」を設置するとともに、「自動融雪剤散布装置」を設置する工事となっております。
工事完了は降雪前の平成25年11月末を予定しています。
“たくさんのご意見・要望をいただきました”
「市民と議員の懇談会」を開催
奥州市議会では、「議会基本条例」に基づき、「市民の意見を市政に反映させる」「しっかりと討議する議会」「市民に開かれた議会を目指す」を議会活動の3つの柱とし活動しております。
「市民と議員の懇談会」は市民が議会を身近に感じてもらうために開催するもので、今回で5回目を迎えました。(懇談会の内容は取りまとめ後、奥州市議会のホームページに掲載します。)
17ページ

おうしゅう市議会だより第29号 17ページ (PDFファイル: 547.8KB)
平成24年度奥州市議会政務調査費収支報告
平成24年4月~平成25年3月
政務調査費は、地方自治法の規定により議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
当市においては、会派又は会派に所属しない議員に対して1人月額1万2千円、年額で14万4千円支給されます。
使途基準が定められており、年度末に収支報告書が提出されます。収支報告書には領収書の添付が義務付けられており、使途基準に基づいた適正な執行に努めております。
奥州市議会では、平成21年9月に制定された議会基本条例の規定に基づき、政務調査費の使途を公開することになっており、所定の手続きにより収支報告書、領収書等の閲覧をすることができます。詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
なお、地方自治法の改正により、平成25年3月1日から政務調査費の名称が政務活動費と変更になりました。
問い合わせ先
(代表)24-2111 内線611
議会日誌
- 4月3日議会広報編集委員会
- 4月9日 議会広報編集委員会
- 4月15日 議会改革検討委員会
- 4月17日 議員全員協議会
東日本大震災調査特別委員会 - 5月13~14日 議会広報編集委員会行政視察
- 5月15日 議員全員協議会
市政調査会
総務常任委員会 - 5月20日 教育厚生常任委員会所管事務調査
- 5月21~23日 総務常任委員会行政視察
- 5月22日 産業経済常任委員会所管事務調査
- 6月4日 議会運営委員会
市民と議員の懇談会(羽田・真城・岩谷堂・田原・古城地区センター) - 6月5日 市民と議員の懇談会(水沢・玉里・前沢・小山・衣川地区センター)
- 6月17日 議員全員協議会
- 6月19日 市政調査会意見交換会
- 6月26日 ILC建設候補地の現地視察
- 6月28日 「除染情報プラザ」研修視察
平成25年第2回定例会(6月7日~6月24日) <会期中に開催された委員会>
- 議会運営委員会 2回
- 競馬事業調査特別委員会 1回
- 東日本大震災調査特別委員会 2回
- 岩手県南広域振興局の誘致についての請願審査特別委員会 1回
- 総務常任委員会 2回
- 教育厚生常任委員会 2回
- 産業経済常任委員会 2回
- 建設環境常任委員会 2回
- 議会広報編集委員会 1回
18ページ

おうしゅう市議会だより第29号 18ページ (PDFファイル: 642.1KB)
私もひとこと
市民にやさしい街へ
前沢区/千田耕平さん
近年、特に目立つ少子化傾向と子育て環境の悪化。不景気の長いトンネルが続く中で、子育て世代の夫婦は共働きが当然の時代となって来ています。
特に問題として思うのは、待機児童問題。私は現在幼稚園でPTA会長を務めさせて頂いていますが、全日保育を受けられず働くに働けない皆さんの声を度々耳にします。
先日、横浜市の待機児童0(ゼロ)実現のニュースが報道されました。共働きを希望する夫婦の要望が届くことは、家庭安定のみならず税収の増加、人口増加のメリットになると思います。児童保育の充実も同じです。
私達の思う良い社会と、市政の間には大きなずれがあるようにも思えます。もっと市民の声に耳を傾ける議会であればと思います。
高齢者問題もこれからどんどん増えて来ると思います。先を見すえた市独自の政治と街づくりが今こそ必要ではないかと思っています。
災害のない奥州市を願って
江刺区/明神キヨ子さん
岩手・宮城内陸地震から5年。東日本大震災から2年3ヶ月が経過しました。これらの災害を踏まえ奥州市は「奥州市地域防災計画」を策定しています。私は防災会議の一員としてこの防災計画を読ませて頂きました。奥州市でも地震による地盤沈下や、大雨、台風による洪水災害、集中豪雨等による土砂災害が懸念されますが、目を疑ったのは土砂災害での、急傾斜地崩壊危険箇所が市内に507箇所あり、そこで950戸の世帯が生活していること。また土石流危険渓流が390箇所、571戸もあるということです。そこで暮らしている人々は、そのような危険な場所であることを知っているのでしょうか。また避難場所は把握できているのでしょうか。
災害はいつどこで発生するか予想できません。市は各地域の避難場所等を、できる限り市民に知らせて頂きたいと思います。
「自助」「共助」が市民の間で機能し、災害のない奥州市であることを願ってやみません。
あとがき
日出ずる山、北上山地。この地におけるご来光は、北上山地から昇る日の光であります。その山々の頂を、最近は特別な思いをはせて見つめます。取りも直さず、国際リニアコライダー、いわゆるILC東北誘致への期待がいよいよ高まっているからであります。
太古の昔から、人々は山の恩恵を受けて暮らしてきました。その自然の恵みに感謝し、山や森に対して畏敬の念を込め崇拝してきました。今注目を集めているこの北上山地は、その自然の豊かさに加え、地質の特異性であります。学者たちも頬ずりしたくなるような花崗岩で形成された硬くて安定した地層。この山の地下深くで、地球誕生のメカニズムを解明しようとするものです。山の恵みは最新の科学の発展にも寄与することとなりましょう。
ILC東北誘致に向け、ここしばらくはご来光に手を合わせ祈りたくなる日が続きます。
(編集委員 小野寺隆夫)
議会広報編集委員会
- 委員長
菅原 明 - 副委員長
小野寺 隆夫 - 委員
- 菅原 由和
- 飯坂 一也
- 佐藤 郁夫
- 中西 秀俊
- 千葉 悟郎
- 藤田 慶則
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-








更新日:2023年09月29日